「日本初の全身麻酔手術を成功させた外科医・華岡青洲。
その裏で、妻の加恵が麻酔薬の実験台となり失明した──」
この物語は、多くの人が一度は耳にしたことがあるはずです。
小説やドラマ、映画でも繰り返し描かれ、青洲の偉業の影にある“悲劇”として強烈な印象を残してきました。
しかし近年の研究を精査すると、この話はどうやら単純な事実ではなさそうなのです。
そこで今回この記事では
- 有名な逸話の真相を史料と薬理学から再検討、薬の副作用と史実の両面
から真実に迫りましたので、ぜひ最後まで読んでいってください!
それでは、早速始めましょう!
華岡青洲の妻は本当に失明したのか?史実と薬理学から真実に迫る!
史料が示す「失明したのは妻ではなく義母」説
実は「妻が失明した」という記録は、一次史料からははっきりとは読み取れません。
現存する青洲の手術録『乳巖治験録』や門人の記録には、確実に「妻が失明した」と断定できる記述は乏しいのです。
むしろ、初期の伝承や写本の中には「義母(於継)が重篤となり失明した」との記録が散見されます。
つまり、犠牲となったのは妻ではなく義母だった可能性が高いというのが、近年の医史学研究で支持されつつある説なのです。
この混乱の大きな理由は、明治以降の研究者による伝聞集や、1966年に発表された有吉佐和子の小説『華岡青洲の妻』にあります。
小説の成功により「妻が失明した悲劇」が物語化され、その後の映画やテレビドラマによって国民的に定着してしまいました。
薬理学から見た「失明の可能性」
青洲が開発した麻酔薬「通仙散(麻沸散)」の主成分は、チョウセンアサガオ(曼荼羅華)、トリカブト(附子)、天南星などと伝えられています。
これらのうち、特に失明に直結するリスクを持つのが曼荼羅華に含まれる抗コリン性アルカロイド(スコポラミン、ヒヨスチアミン、アトロピンなど)です。
これらの成分は瞳孔を拡大させ、房水の排出を妨げることで眼圧を急激に上昇させます。
前房が浅い眼の人では急性閉塞隅角緑内障発作を起こし、治療が遅れると短期間で不可逆的な失明に至るのです。現代眼科学でも、この副作用は広く認められています。
さらに、附子のアコニチン系アルカロイドには強い心毒性・神経毒性があり、繰り返し投与すれば生命に関わる重篤な副作用を招く可能性が高いことも知られています。
つまり「麻酔薬の副作用で視力を失った」というシナリオ自体は、薬理学的には十分に成立するのです。
史実とフィクションが交錯した理由
- 一次史料の限界:口承伝承と写本が混ざり、年代ごとに記述の差異が大きい。
- 近代の再構成:呉秀三らの伝聞集、矢数道明らのまとめを経て物語が整理されていった。
- 大衆文化の影響:有吉佐和子『華岡青洲の妻』(1966)が決定打となり、フィクションとしての“妻の犠牲”像が定着した。
その結果、「誰が失明したのか」という点が不明瞭になり、史実と創作が結びついてしまったのです。
まとめ
- 「妻・加恵が失明した」という話は、実は近現代の創作や伝承で拡大されたものである。
- 史料を精査すると、失明したのは義母・於継であった可能性が高い。
- 通仙散に含まれる曼荼羅華などの成分は、薬理学的に急性緑内障→失明を引き起こす可能性を十分に持つ。
- つまり、「薬の副作用で失明した」は医学的に妥当な説明だが、“誰が犠牲になったか”は再検討が必要。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
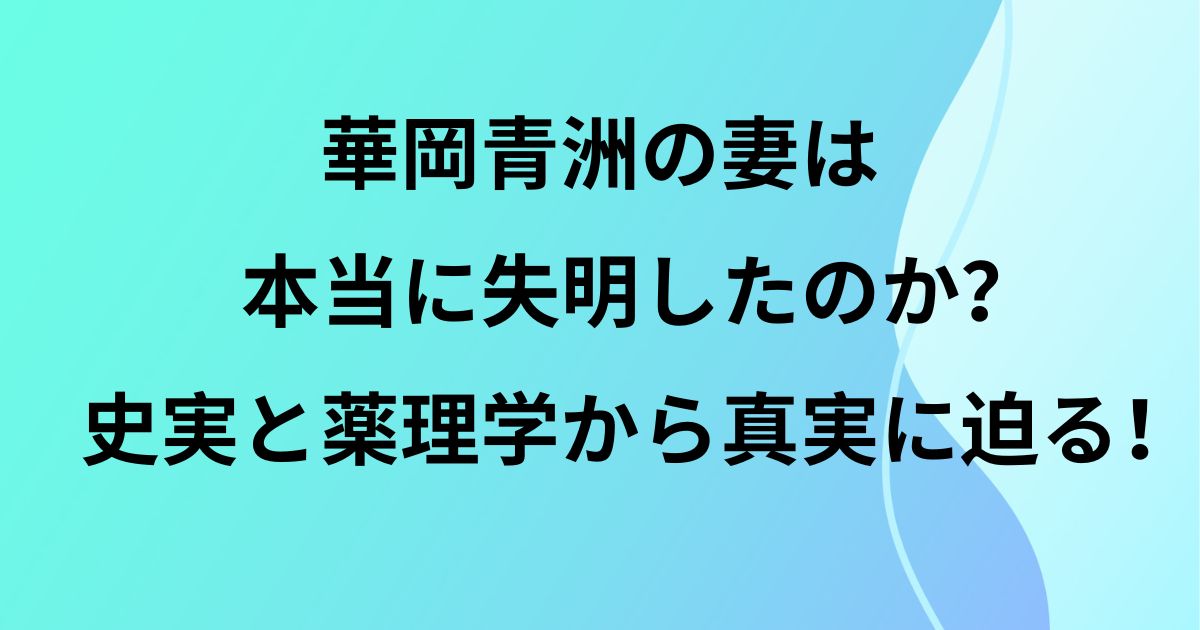
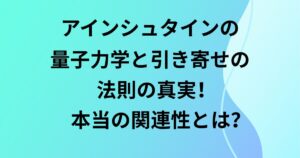
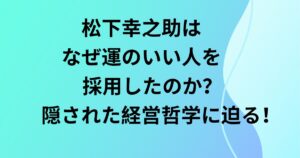
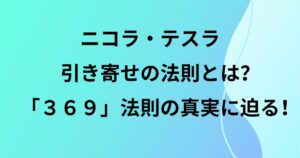
コメント